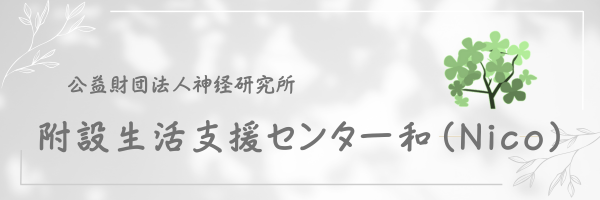Facility Introduction施設のご案内

附設生活支援センター和(Nico)について
1951年に内村祐之先生により設立された公益財団法人神経研究所は、その理念の下に、民間による精神医学(神経科学・睡眠医学を含む)研究機関の先駆的存在として、国民の精神的健康を図ることを目的として活動しています。
発達障害専門外来を開設する附属晴和病院では、診断後のケアを重視することが重要と考え、「治す医療」から「治し支える医療」への転換を図っています。
患者さんにとって日常生活、学び、仕事を通じて、社会につながる切れ目のないサービスの提供を目指し、2025年の晴和病院の再始動を機に、福祉事業を展開します。
医療機能を有する晴和病院を支える施設という意味も込め、展開する福祉施設には地域活動支援センター晴(Halu)と附設生活支援センター和(Nico)と名付けられました。
和(Nico)では、利用者だけでなく、親御さん、支援スタッフ、地域関係者の皆さまがニコニコ過ごしていけるような環境づくりも併せて行っていきます。

自立訓練(生活訓練)
地域で安心して暮らしていくために必要な「生活力」「人とのつながり」「働く力」を育てるための訓練や相談等を提供します。通所型での支援にはなりますが、日常生活の基礎作りから社会参加までを段階的にサポートします。
・生活の基礎づくり:食事・睡眠・身だしなみなど、日々の生活を整える力
・自分の生活をつくる力:金銭管理、衣食住の選択、生活の自己決定
・自分自身の理解:障害や特性への理解、人間関係やコミュニケーションの工夫
・地域とのかかわり:就労準備、余暇活動、地域資源の活用
・権利の活用:社会保障制度や福祉制度の理解と活用方法

宿泊型自立訓練
将来的に一人暮らしやグループホームなどで安心して生活できるようになるための「生活の練習の場」です。
一定期間、支援付きの住環境で生活しながら、日常生活に必要なスキルを身につけていきます。
通所型の自立訓練(生活訓練)との違いは、宿泊型自立訓練は特にプログラムがある訳ではなく、日々生活していくことそのものが訓練です。
・生活リズムの安定:毎日の起床・就寝、食事、掃除などを自分で管理する力
・金銭管理:お金の使い方や予算の立て方を学び、無理のない生活を送る力
・セルフケア:身だしなみや健康管理を自分で行う力
・対人関係の構築:他者との関わり方やマナーを学び、安心して人とつながる力
・地域との関わり:買い物や外出、余暇活動などを通じて地域社会に参加する力
入居にあたっては、月額家賃、水道光熱費(実費)等の費用もかかります。

サポート方針
利用者一人ひとりの特性や目標に応じた個別支援を行い、できることを増やすだけでなく、苦手なことへの工夫や援助の求め方を学びながら「自分の暮らしを自分でつくる力」を育みます。
「親なきあと」に備え、本人が自分の生活を自分で築いていけるよう、母体の医療機関での知見を活かし、精神科デイケアや地域の社会資源とも連携しながら、発達障害・精神障害のある方が地域で主体的に生活できるよう支援します。
フォトギャラリー